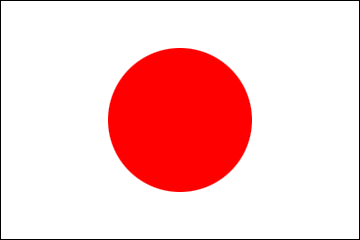日本舞踊解説付きデモンストレーションの開催(2022年11月21日)
令和4年11月16日
 ©️KISHIN SHINOYAMA
©️KISHIN SHINOYAMA
開催概要
日時:2022年11月21日(月)19時30分より
会場:Narodni dom Maribor, Dvorana generala Maistra
住所:Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
主催:在スロベニア日本国大使館、Narodni dom Maribor、国際交流基金
入場無料
会場:Narodni dom Maribor, Dvorana generala Maistra
住所:Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
主催:在スロベニア日本国大使館、Narodni dom Maribor、国際交流基金
入場無料
先生方のプロフィール
【桜井多佳子氏】
舞踊評論。大阪生まれ。ロシア国立劇場芸術大学研修。日経新聞、ダンスマガジンほかに執筆。海外取材は38ケ国。ペルミ(ロシア)国際バレエコンクールプレス審査員、ヴィチェフスク(ベラルーシ)国際振付コンクールプレス審査員ほか。文部科学省文化審議官、(独)日本芸術文化振興会舞踊プログラム・オフィサー、文化庁芸術祭審査員などを歴任。著書に『感じるバレエ』、共著に『ロシアの文化・芸術』『バレエ・ギャラリー30』。
【藤間蘭黄氏】
江戸時代から続く日本舞踊の家に生まれ5歳から祖母、藤間藤子(重要無形文化財保持者)、母蘭景より踊りの手ほどきを受ける。6歳で初舞台。16歳で藤間流名取となり、長唄、能楽、囃子、茶道の研鑽も積む。25歳で師範免許取得。初心者から師範まで幅広く指導している。
曽祖母や祖母から伝わる古典の継承とともに、ゲーテの「ファウスト」を一人で演じる『禍神』、オペラ「セビリアの理髪師」の舞台を江戸に移した『徒用心』、ムスルグスキーのピアノ曲とともにバレエ・ダンサーと演じた『展覧会の絵』など創作作品も積極的に発表している。祖母の代から海外活動も精力的に行い、北・南米、アジア、中東、ヨーロッパで幅広く日本舞踊を紹介している。
2015、17、19年には世界ダンサー、ファルフ・ルジマトフ、ロシアの国立バレエ団の芸術監督、岩田守弘との『信長』を東京で上演。2019年1月にはロシアの3都市で6公演を成功させた。2015年芸術選奨文部科学大臣賞。2016年文化庁文化交流使。2019年度日本藝術院賞。2020年秋、紫綬褒章。
舞踊評論。大阪生まれ。ロシア国立劇場芸術大学研修。日経新聞、ダンスマガジンほかに執筆。海外取材は38ケ国。ペルミ(ロシア)国際バレエコンクールプレス審査員、ヴィチェフスク(ベラルーシ)国際振付コンクールプレス審査員ほか。文部科学省文化審議官、(独)日本芸術文化振興会舞踊プログラム・オフィサー、文化庁芸術祭審査員などを歴任。著書に『感じるバレエ』、共著に『ロシアの文化・芸術』『バレエ・ギャラリー30』。
【藤間蘭黄氏】
江戸時代から続く日本舞踊の家に生まれ5歳から祖母、藤間藤子(重要無形文化財保持者)、母蘭景より踊りの手ほどきを受ける。6歳で初舞台。16歳で藤間流名取となり、長唄、能楽、囃子、茶道の研鑽も積む。25歳で師範免許取得。初心者から師範まで幅広く指導している。
曽祖母や祖母から伝わる古典の継承とともに、ゲーテの「ファウスト」を一人で演じる『禍神』、オペラ「セビリアの理髪師」の舞台を江戸に移した『徒用心』、ムスルグスキーのピアノ曲とともにバレエ・ダンサーと演じた『展覧会の絵』など創作作品も積極的に発表している。祖母の代から海外活動も精力的に行い、北・南米、アジア、中東、ヨーロッパで幅広く日本舞踊を紹介している。
2015、17、19年には世界ダンサー、ファルフ・ルジマトフ、ロシアの国立バレエ団の芸術監督、岩田守弘との『信長』を東京で上演。2019年1月にはロシアの3都市で6公演を成功させた。2015年芸術選奨文部科学大臣賞。2016年文化庁文化交流使。2019年度日本藝術院賞。2020年秋、紫綬褒章。
演目概要
『都鳥』
都鳥は、隅田川に飛び交うユリカモメです。この曲は江戸の隅田川の風景を描写した踊りです。
行き交う船の中での茶会、宴会。荷揚げ人足の力持ち、大きな帆掛船などの様子が描かれます。後半のラブシーンでは、日本舞踊の特徴を生かして、踊り手は、男性役と女性役の両方を演じます。
近代化した明治時代の人がちょっと前の江戸を思い出し、哀愁に浸る作品です。
『松の翁』
「松」は松の木。「翁」は一般的には老人を意味し、日本の伝統芸能の一つである能楽の演目タイトルとしても有名です。この曲の作詞・作曲は、邦楽の一ジャンル、長唄の巨匠である三代目杵屋正次郎です。作者が、裕福な友人松永安彦の邸宅を訪れたとき、壮大な庭園の風景に深く感動し、インスピレーションを得て、19 世紀半ばに作りました。
前半では、松永邸の庭園「万樹園」の木々の美しさや富士山の雄大な景色を、能「翁」の荘厳さに例え、その後、五穀豊穣を祈る三番叟のパートがリズミカルに踊られます。後半の、庭の松の木の姿、水の流れ、舞い散る落ち葉に至る表現も見所です。
『変身』
朝起きると男性は、巨大な虫になっていた。家族思いの真面目な営業マンが、いつも通りに目を覚ました朝、虫になってしまったのだ。パニックに陥る家族。妹は兄の好物を与えるがその虫は食べず、ゴミを好んで食べる。訪ねてきた上司は、止める父の手を振り切って彼の部屋に入り、虫の姿に驚く。そして父がリンゴを投げつけ、毒虫は死んでしまう。家族は悲しむ。が、やがて安堵し、明るく生きていく。
虫になる男性、とともに周囲の人間たちの様子を日本舞踊の特徴を生かしてひとりで描く。バルトークのピアノ曲で、文学を日本舞踊化します。
都鳥は、隅田川に飛び交うユリカモメです。この曲は江戸の隅田川の風景を描写した踊りです。
行き交う船の中での茶会、宴会。荷揚げ人足の力持ち、大きな帆掛船などの様子が描かれます。後半のラブシーンでは、日本舞踊の特徴を生かして、踊り手は、男性役と女性役の両方を演じます。
近代化した明治時代の人がちょっと前の江戸を思い出し、哀愁に浸る作品です。
『松の翁』
「松」は松の木。「翁」は一般的には老人を意味し、日本の伝統芸能の一つである能楽の演目タイトルとしても有名です。この曲の作詞・作曲は、邦楽の一ジャンル、長唄の巨匠である三代目杵屋正次郎です。作者が、裕福な友人松永安彦の邸宅を訪れたとき、壮大な庭園の風景に深く感動し、インスピレーションを得て、19 世紀半ばに作りました。
前半では、松永邸の庭園「万樹園」の木々の美しさや富士山の雄大な景色を、能「翁」の荘厳さに例え、その後、五穀豊穣を祈る三番叟のパートがリズミカルに踊られます。後半の、庭の松の木の姿、水の流れ、舞い散る落ち葉に至る表現も見所です。
『変身』
朝起きると男性は、巨大な虫になっていた。家族思いの真面目な営業マンが、いつも通りに目を覚ました朝、虫になってしまったのだ。パニックに陥る家族。妹は兄の好物を与えるがその虫は食べず、ゴミを好んで食べる。訪ねてきた上司は、止める父の手を振り切って彼の部屋に入り、虫の姿に驚く。そして父がリンゴを投げつけ、毒虫は死んでしまう。家族は悲しむ。が、やがて安堵し、明るく生きていく。
虫になる男性、とともに周囲の人間たちの様子を日本舞踊の特徴を生かしてひとりで描く。バルトークのピアノ曲で、文学を日本舞踊化します。